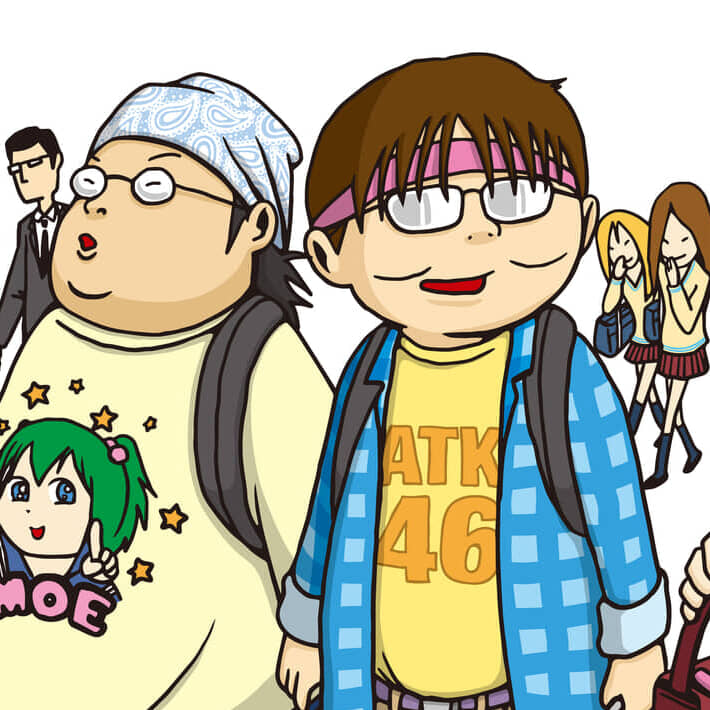国際結婚から投資、政治の右左…人間の選択は「遺伝子」で決まっていた説【中野信子】
『脳はどこまでコントロールできるか?』より #2
■「DRD」と国際結婚の関係
このドーパミン受容体、なかでもDRD4については、多くの科学者が注目しています。なぜなら、これが、人間の購買行動を左右するものであるので、マーケティングにとって非常に重要な要素でもあり、さらに経済行動におけるリスクテイキングの指標ともなり得るからです(たとえば、大きな株の取引などでハイリスク・ハイリターンの賭けに出られるのかどうかなど)。
また社会学においては外人嫌いかどうか、心理学においてはもちろん新規性追求、さらには政治行動におけるリベラルの度合い(これはDRD4ではなくDRD2という別のサブタイプですが)などもわかるという、人間の社会的行動の多くの側面を説明できる神経科学的要素だからです。
さらに、おもしろいのは、DRD4の繰り返し頻度が高い人では国際結婚をする傾向が高くなるという点もあげられます。恋する相手・結婚相手に自分になければそのものや新しいものを求めて恋に落ちるというタイプの人は、このタイプの脳の持ち主かもしれませんね。
繰り返し回数の多い人の振る舞いとして特徴的なのは、新しもの好きであること、異性に目移りしがちなこと、飽きっぽいこと、ハイリスク・ハイリターンの勝負を好むこと、などです。こうした性質は、うまくコントロールすれば仕事がとてもできる人として評価を上げるでしょう。
しかし、一歩間違うとただのギャンブラーになりかねない、という側面があるのも否めません。自分の特質を知って、上手に自分の脳を使いこなしていきたいものですね。
ところで、人の遠い先祖である原猿類では、ドーパミン受容体における繰り返し回数は1回程度ですが、より高等な類人猿ほど、ドーパミン受容体の繰り返し回数が増えています。繰り返し回数が多いと好奇心旺盛になることを考えてみると、それまでの生活に飽き足らず、より新しい世界へ、新しい世界へと開拓を続けてきた種の末裔が人類と言えるのかもしれません。
文:中野信子
〈『脳はどこまでコントロールできる?』より構成〉
- 1
- 2